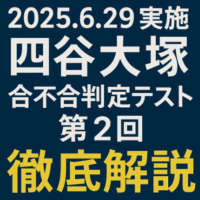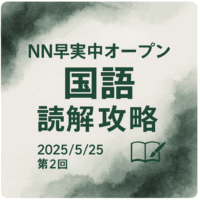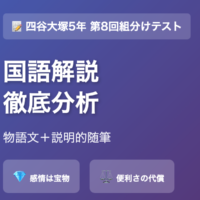- ホーム
- 模試・塾テキスト解説
- 6/2(日)実施 日能研全国公開模試 大問3 説明文 文章解説
6/2(日)実施 日能研全国公開模試 大問3 説明文 文章解説
本文の要約
この文章では、過去問の重要性を「具体」と「抽象」という二つのレベルで説明しています。具体的な問題を解くことは試験対策の一部であり、過去問を通じて試験の「傾向」を把握することが大切だと述べています。傾向とは、出題範囲、形式、量、順番、構成などであり、これらを理解することで、試験全体のバランスや関係性を見極めることができるのです。さらに、歴史の学び方とも関連付け、具体的な事実を暗記するだけでなく、抽象的にその流れや関係性を理解することが重要であると述べています。
重要語句
- 具体(ぐたい):物事をはっきりとした形や内容で示すこと。
- 抽象(ちゅうしょう):具体的な形や内容を離れて、物事の共通点や本質を捉えること。
- 傾向(けいこう):ある方向に物事が進む様子。
- マークシート形式(まーくしーとけいしき):選択肢にマークをして答える形式。
- 記述式(きじゅつしき):自分で文章を書いて答える形式。
筆者の主張
筆者は、過去問を解くことの重要性を強調しています。具体的な問題を解くことだけでなく、その背後にある傾向や抽象的なパターンを理解することが重要であると述べています。さらに、この考え方は歴史の学び方にも通じるもので、歴史的事実を単に暗記するのではなく、その流れや関係性を理解することで、現在や未来に応用できると主張しています。
対比表現の分析
文章中には、具体的な問題と抽象的な傾向の対比が繰り返し使われています。具体的な問題は個々の事実や事例を指し、抽象的な傾向はそれらを統合した全体のパターンや流れを指します。この対比によって、試験対策における具体的な演習と抽象的な理解の両方の重要性が強調されています。
主題と要点
主題は「過去問を通じて試験の傾向を把握することの重要性」と「具体的な事実と抽象的な関係性の理解の必要性」です。これにより、試験だけでなく、歴史や他の学びにおいても具体と抽象の両方の視点を持つことが重要であると述べています。
まとめ
試験対策において過去問を解くことは、具体的な問題の練習だけでなく、試験の傾向を理解するための重要な手段です。この考え方は歴史の学びにも応用でき、具体的な事実と抽象的な関係性の両方を理解することで、より深い学びを得ることができます。試験や歴史の学びにおいて、具体と抽象の視点を持つことが成功への鍵となります。
今回の文章を通じて「試験」というテーマ以外にも具体と抽象を当てはめて考えられるようになると良いですね。