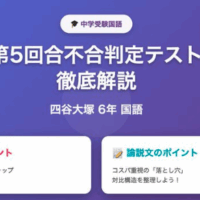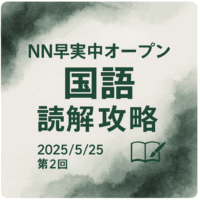- ホーム
- 模試・塾テキスト解説
- 6/2(日)実施 日能研全国公開模試 大問4 説明文 文章解説
6/2(日)実施 日能研全国公開模試 大問4 説明文 文章解説
概要
堀江敏幸の『歌でも読む様にして』は、日本の高い識字率と文字の力について論じた文章です。この文章は、文字の読み書きができることが心を理解する力とは直結しないというテーマを扱っています。文章中では、具体的なエピソードを通じて、文字を介したコミュニケーションの重要性と、その背景にある感情の伝達について述べています。
重要語句
- 識字率(しきじりつ):15歳以上の人口のうち、読み書きができる人の割合を示す指標。
- 人災(じんさい):人為的な原因による災害。
- 無為(むい):何もせずにぼんやりと過ごすこと。
- 些事(さじ):取るに足らないこと。
- 候文(そうろうぶん):「です」「ます」を「候(そうろう)」という言い方に換えた文。昔は手紙など書き言葉のみで使われていた。
注目すべき表現
- 識字率という物騒な単語:識字率が単なる統計データではなく、人々の生活や心に関わる重大かつ煩わしい問題であることを示す表現。
- 歌でも読む様にして:父親が恭三に手紙を読むように頼む際の表現。文字の情報以上に、その背景にある感情を伝えたいという思いが込められている。
筆者の主張
堀江敏幸は、文字の読み書きができることと心を理解する力が直結しないことを強調しています。特に、恭三と父親のエピソードを通じて、文字が単なる情報の伝達手段にとどまらず、感情や思いを伝える大切なツールであることを示しています。
定義文
「読み書き【とは】本来無駄なことを無駄でなくするための力なのだ」という表現は「読み書き」の定義(言葉の意味を説明)をしています。無駄なこと=候文の定型を並べただけの手紙 無駄でなくする=文字を片端から読んで聞かせてくれりゃうれしいのじゃ(書き手の感情を感じ取る)と解釈すると全体像が見えてくるでしょう。
作品のテーマと要旨
この文章のテーマは、「文字の力とその背景にある感情の伝達」です。文字は情報を伝えるだけでなく、感情や思いを伝える重要な手段であることを、恭三と父親のエピソードを通じて読者に伝えています。
読み方のアドバイス
この作品を読む際には、登場人物の心情や行動に注目し、比喩表現や対比表現を理解することが重要です。また、筆者が何を伝えたいのかを考えながら読むことで、作品のテーマや主張を深く理解することができます。特に、父親の「歌でも読む様にして」という言葉の意味を噛みしめることで、文字の持つ力とその背景にある感情の深さを感じ取ることができるでしょう。
物語と同じように人物の心情や人物像を正確につかみ、比ゆ表現に注目することでメインとなるテーマが見えてくるようになります。線引きなど意識して取り組むようにしましょう。