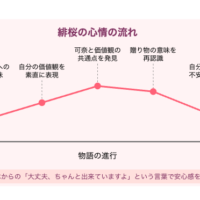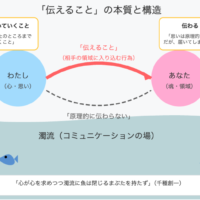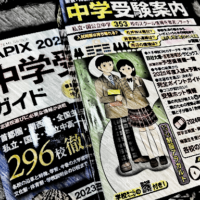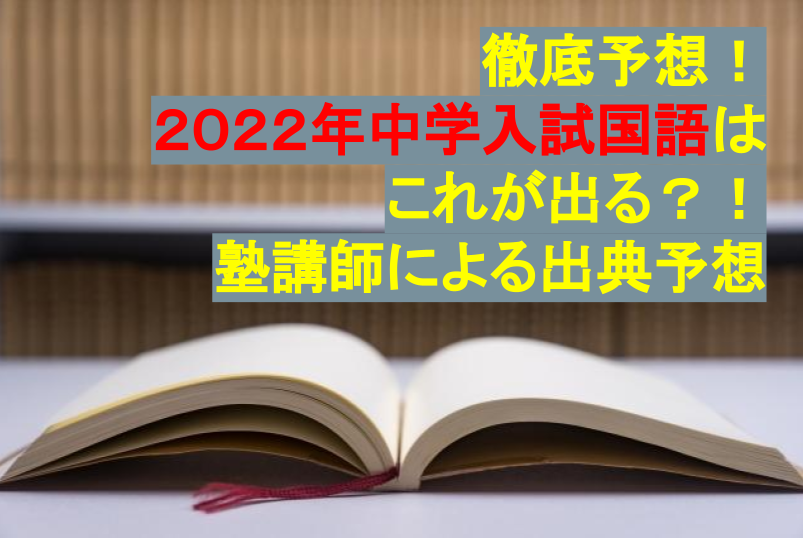小4・小5から始める渋幕の国語対策ロードマップ
― 過去10年の出典と文学史から逆算する準備法 ―
はじめに: 渋幕国語が見ている力
渋幕が大切にしているのは「自調自考(自分で調べて自分で考える)」です。国語では、難度の高い評論・随筆や、心理の揺れを丁寧に追う文学作品を素材に、「根拠を示して考える」姿勢を確かめます。
学校の教育目標そのものが出題方針の土台になっているのです。
とはいえ、渋幕国語の出典・文学史知識の難易度は御三家中を上回る他に類を見ない高さであり、小学生が対応するには困難を極めます。一般的な塾の国語のカリキュラムでは対応しきれないのが現状です。では合格者はどのような対策をしているのか?
合格者の傾向を見ていくと、多くの生徒はごく自然に文学的な知見を身につけています。
芥川龍之介や夏目漱石と行った文豪たちの文章は時代背景が古く、子どもには読みづらく感じられることも多いですが、内容は決して子どもが理解できない物ではありません。
早い段階でこういった作品を「おもしろい」と感じ、自ら読み進めたくなる環境が整っている子が合格に向けて有利であるのは間違いないでしょう。
こうした環境を整えるために必要な情報を以下に整理ました。渋幕突破を目指す環境作り、早めに着手しましょう。
1. 過去10年の出典
- 2025:随筆=永井玲衣『水中の哲学者たち』/物語=安岡章太郎「球の行方」(『走れトマホーク』所収)。
- 2024:物語=志賀直哉「或る朝」(ちくま日本文学)
- 2023:物語=津島佑子「鳥の涙」
- 2022:一次=桑原武夫「ものいいについて」/平野啓一郎『本心』、二次=藤田正勝『はじめての哲学』/古内一絵『星影さやかに』
- 2021:一次=湯川秀樹「具象以前」(『詩と科学』)/菊池寛「極楽」、二次=岸見一郎「人生は苦である、でも死んではいけない」/上林暁「薔薇盗人」
- 2020:一次=大澤真幸「『空気』の研究—『忖度』の温床」/三島由紀夫『春の雪』(『豊饒の海』第一巻)、二次=中屋敷均『科学と非科学』
- 2019:一次=寺田寅彦『天災と国防』/若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』
- 2018:一次=養老孟司『養老孟司の幸福論 まち、ときどき森』/芥川龍之介「死後」、二次=内田樹『街場の共同体論』/遠藤周作「犀鳥」
- 2017:物語=川端康成「めずらしい人」(『掌の小説』)
- 2016:夏目漱石『こころ』(抜粋)/福田恆存「悪に耐える思想」
2. 小4・5のうちに“読書体力”をつくる進め方
学年別の道筋(目安)
- 小4~小5の春:古典~近現代の短編中心で土台づくり(本稿「第I群」)。
- 小5~小6の夏:心理描写が濃い作品+論説の型を覚える(「第II群」「第III群」)。
- 小6の秋~冬:過去問で実際の出題に触れる+発展的な随筆・評論をすき間時間で読む(「第IV群」)。
読書のコツ(小学生向けの言い換え)
- 短い話から始める:1週間で読み切れる分量を選ぶ。
- 背景を調べる:いつの時代・どんな場所の話かを先に知る。
- 心の変化を追う:「なぜそう思ったか?」を自分に問いかける。
- 古い文体は音読:声に出すと意味がつながりやすい。
- 記録を残す:出典・要旨をメモする。
3. まずはここから:基礎〜中級のおすすめ短編(小4・5向け)
目的は「読み切る→考えを言葉にする」経験を積み重ねること。
1作につきあらすじ3行+心情の変化を必ずメモする。
第I群:基礎(短編で“読む筋肉”をつける)
- 芥川龍之介「蜘蛛の糸」…人の欲と救い。短くても問いが深い。
- 芥川龍之介「杜子春」…お金と生き方の関係を考える入口。
- 太宰治「走れメロス」…約束・信頼の王道テーマ。
- 芥川龍之介「羅生門」…生きるために“善悪”はどう揺れるか。
- 芥川龍之介「鼻」…劣等感の扱い方を学ぶ。
- 夏目漱石『こころ』(冒頭)…「先生」と「僕」の距離感(※2016出典)
- 志賀直哉「清兵衛と瓢箪」…好きの力と大人の視線。
- 川端康成「めずらしい人」…老いと親子の機微(※2017出典あり)。
- 芥川龍之介「死後」…抽象的テーマへの入口(※2018出典)。
- 志賀直哉「菜の花と小娘」…情景描写と心の結びつき。
第II群:中級(視点・構成を意識する)
- 芥川龍之介「トロッコ」…思い出と後悔;時間の経過で読みが深まる。
- 志賀直哉「城の崎にて」…観察から死生観へ。
- 菊池寛「極楽」…“幸福とは何か”を問う(※2021出典)。
- 芥川龍之介「お律と子等と」…家族の距離感。
- 芥川龍之介「蜜柑」…象徴の読み方(色・物・景)。
4. 小6夏以降に向けて:“渋幕で実際に出た/類似”作品で深める
小5の終わり〜小6で、以下のような出題作や近縁ジャンルを少しずつ。
第III群:上級&論説の型(※学び方を先に決める)
- 志賀直哉「或る朝」(2024出題)…日常の中の微細な心理。
- 三島由紀夫『豊饒の海①春の雪』(2020出題)…冒頭だけでも難語と比喩に慣れる。
- 平野啓一郎『本心』(2022出題)…近未来の倫理を考える。AIの発展とも関連。
- 若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』(2019出題)…“老い”を他者の立場で読む訓練。
- 藤田正勝『はじめての哲学』(2022二次)…論説の基本構造を掴む。
- 寺田寅彦『天災と国防』(2019出題)…科学的思考×社会。
- 養老孟司『…幸福論 まち、ときどき森』(2018出題)…随筆で論を追う。
- 大野晋『日本語練習帳』…ことば=思考を実感。
- 齋藤孝『声に出して読みたい日本語』…名文の知識を身につける。
- 「時間」を扱う入門書(例:講談社新書系)…頻出テーマの横断。
第IV群:発展(直前期に“最新傾向×難素材”)
- 永井玲衣『水中の哲学者たち』(2025一次出題)…随筆で自ら問いを立てて読む。
- 志賀直哉『暗夜行路』…長編で構成をつかむ。
- 太宰治短編集(メロス以外)…作風の幅を知る。
- 太宰『人間失格』(抜粋)…語り手の距離感を学ぶ。
- 室生犀星「鮎のかげ」…心情と情景の交点。
5. 文学史・文学賞の出題ポイントだけ押さえる
暗記ではなく、「作品理解につながる基礎常識」をコンパクトに。
- 芥川賞と直木賞の違い
芥川賞=雑誌発表の純文学の中短編(新人中心)/直木賞=エンタメ系の単行本(新進〜中堅)。いずれも年2回(7月・翌年1月)。最新情報は主催団体の公式FAQで確認。 - 創設:1935年、菊池寛が両賞を制定(のち日本文学振興会が運営)。
- 直近トピック:第173回(2025年上半期)は両賞とも「該当作なし」。毎年1月中旬前後の発表は入試直前期のチェック対象。
- 日本のノーベル文学賞:川端康成(1968)と大江健三郎(1994)。受賞の要旨・公式ページが読みの手がかり。
まとめ
渋幕の国語は、単なる「読解力」ではなく、自ら考える力を問う入試です。
過去10年の出典を見ても、文学・哲学・科学・倫理など、幅広い分野を通して「人間とは何か」を考えさせる文章が中心になっています。
こうした問題に対応するには、塾のカリキュラムだけに頼らず、家庭で“読書体力”を育てる時間を早い段階から確保することが大切です。
短編から始めて読書の習慣を整え、時代背景や作者の考え方に触れる経験を積むことで、
受験時に渋幕国語にふさわしい思考の深さが身についていきます。
読書は「正解を出す練習」ではなく、「自分の言葉で考える練習」です。
小4・小5のうちに文学や随筆に親しみ、「読む→考える→言葉にする」習慣を身につけておくことが、
渋幕合格に向けた最良の準備になります。
渋幕国語対策に関するお問い合わせはこちらから👇