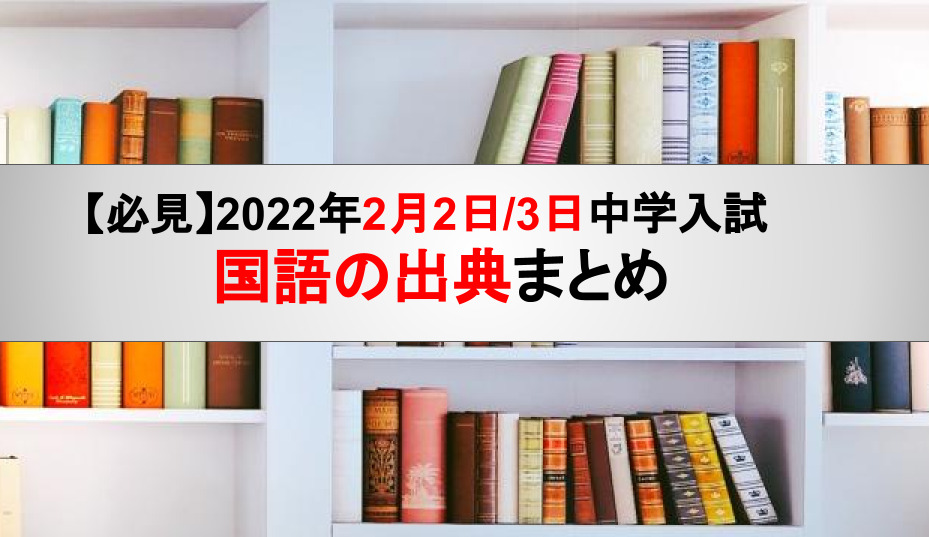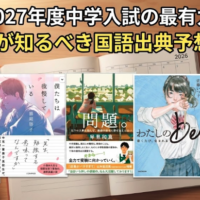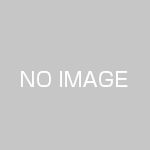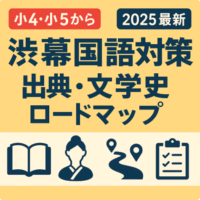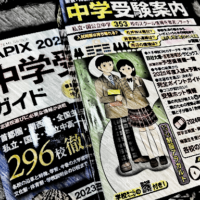2025年度中学入試最多出題!『わからない世界と向き合うために』はなぜこれほど多くの学校で出題されたのか?
2025年度の中学受験国語では中屋敷均『わからない世界と向き合うために』が首都圏を中心に多くの中学校で入試問題の出典に採用され、注目を集めました。今回は、この作品の魅力と入試で扱われた背景と、今後の国語への向き合い方について考えます。
入試での出題校と出題傾向
2025年度入試では私が調べて把握するだけで首都圏の難関校を含む約20校以上でこの作品が出題されました。鴎友学園女子、市川、共立女子、山脇学園、立教女学院、吉祥女子、富士見、桐蔭学園、横浜共立学園、高輪、大妻多摩、明大八王子、昭和秀英、逗子開成、甲陽学院、四天王寺、東大寺学園、など、多くの学校が国語の説明文教材として本文の一部を採用しています 。出典がこれほど多くの学校で重複するのは珍しく、2024年度入試で頻出だった『増えるものたちの進化生物学』(2024年度少なくとも9校で出題:青山学院、学習院、山脇、栄東、カリタス、筑波大付属、など)を上回る異例の扱いとなりました 。
出題形式を見ると、市川中が特徴のある出題をしています。本作品を第1問の説明的文章とし、第2問に別の随筆文を組み合わせる構成が目を引きました 。記述では「なぜ嘘をつくことはいけないのか」を本文に即して説明させる問いなど、筆者の主張の根拠を自分の言葉でまとめさせる問題が見られます。総じて、文章の論旨を正確につかみ、要点を言語化する力が問われる傾向でした。
作品の内容要約~中学受験生に響くテーマ
『わからない世界と向き合うために』は、生物学者である筆者・中屋敷均さんが「予測もコントロールも難しい、思い通りにならないこの世界」にどう向き合うかを語ったメッセージ性の強い内容です 。176ページほどの新書で、第1部「空に吸はれし十五の心」・第2部「私たちの社会の行方」・第3部「科学と非科学の間で」という三部構成になっています。タイトルが示す通り、「先の見えない不確実な世界」への向き合い方が全体を貫くテーマです。
筆者はまず、この世では思いもよらないことが起き、物事は確率通りには進まないと指摘します。つまり、どんなに科学が発達しても将来の不安やリスクを完全になくすことはできないという現実です。ではそんな「わからない世界」にどう対処すべきか、、、筆者は「無謀じゃダメだし、臆病でもいけない!」という姿勢を提唱します。極端な楽観(無謀)や悲観(臆病)に陥らず、適度な勇気と慎重さをもって未知に立ち向かうことが大切だというメッセージです。見えないものに向き合うことこそ生きる意味がある、と前向きに説いており、中学受験を控え変化の多い時期にある子どもたちにも響くテーマと言えるでしょう。
筆者の主張とそれを支えるエピソード
著者・中屋敷氏の主張の核にあるのは、「不確実な世界で主体的に生きるための覚悟」*。筆者は、人生のあらゆる選択にはリスクが伴う以上、「私たちにできることは、ベストの選択をすることではなく、自分の選択をベストにするように生きていくことだけ」だと述べています。つまり、失敗を恐れて「絶対に正しい道」ばかり求めるのではなく、自分で選んだ道を正解にしていく努力こそが肝心だという考え方です。リスクのない選択肢を探し求めるようになると、かえって何も選べなくなってしまう──そんな警鐘とともに、自分の判断に責任を持ち前進する姿勢が説かれます。
この主張をわかりやすく支えているのが、作中で語られる具体的なエピソードです。例えば「嘘をつくこと」と「生きる姿勢」についての筆者の考察がその一つです 。中屋敷氏は「なぜ嘘をつくのはいけないのか?」という問いに対し、嘘をつけば目先の問題は一時しのげるかもしれないが、そんなやり方に慣れてしまうと「いざという時に頑張れなくなってしまう」と述べています。つまり、嘘という行為は人生で否応なく遭遇する困難や苦しみに正面から向き合わず逃れてしまうことと同根であり、習慣化すれば肝心な場面で踏ん張る力を失ってしまうのだ、と筆者は指摘するのです。このように、身近な行動原理である「嘘」を題材にしながら、困難から逃げずに立ち向かう生き方の重要性を具体例を用いて読者に納得させています。
他にも、第1部では「バンジージャンプが飛べない君へ」と題し恐怖心と向き合う話、第3部では「科学はすべてを解き明かしはしない」という章で科学と不確実性の関係を論じるなど、豊富なエピソードが展開されます。これらを通じて一貫して伝えられるのは、「逃げずに未知に挑む態度が、自分自身の成長や幸福につながる」という筆者の信念です。読後には爽やかな前向きさとともに、子どもにも大人にも考えさせられる深い気づきが得られるでしょう。
なぜ入試で多く使われたのか?~普遍性・科学的視点・構成の明快さ
これほど多数の学校が同じ書籍を国語の出典に選んだ背景には、作品テーマの普遍性と内容の良質さがあると考えられます。まずテーマについて、本書は「不安やリスクとどう向き合うか」という時代や世代を超えて重要な問いを扱っています。中学受験生にとっても、これから未知の中学校生活へ踏み出す節目に当たり、「未知の世界を怖がらず、自分の判断で道を切り拓いてほしい」というメッセージは各学校の先生方がぜひ子どもたちに届けたい内容だったのでしょう。実際、入試問題として本書を出題したこと自体が「先生たちからのメッセージ」**であると捉えることもできます。子ども達へ「他者に選択を委ねず、自分次第で選んだ道をベストにしていこう」というエールを、本を通じて送っていたように感じられます。
次に、筆者が生物学者(科学者)である点も見逃せません。本書は科学的な視点と筆者自身の経験談を交えながら綴られており、論説文として論理の筋道が明快です 。昨今の入試国語ではAIや科学、哲学など知的好奇心を刺激し考えさせられるテーマが好まれる傾向があります。中屋敷氏の語る内容は科学リテラシーにも通じ、「科学では予測しきれない世界をどう生きるか」という視点は教育的にも価値が高いものです 。文章全体の構成が論理的で問いを立てやすく、また内容自体も現代社会における思考力を見るのにふさわしいため、出題者にとって扱いやすかったのでしょう。
さらに、筑摩書房の「ちくまプリマー新書」シリーズからの一冊であることもポイントです。ちくまプリマー新書は中高生向けの新書シリーズで、中学入試の説明的文章では頻出のレーベルとして知られています。塾テキストなどで過去に扱われていない新刊本ほど入試で「対策しづらく純粋な読解力を測れる」ため重宝される傾向があり 、2024年2月刊行の本書はまさに格好の素材でした 。実際、「国語も情報戦」と言われるように大手塾では発売後すぐ模試に取り上げられたものの、初見の受験生にとっては未知の文章です。こうした理由から、「テーマの良さ」「文章の質」「新鮮さ」という三拍子が揃った本書が2025年度入試でこれだけ広範囲に採用されたのだと考えられます。
読解対策としての学びと保護者へのアドバイス
入試国語の読解対策としても、この作品から得られるものは大きいです。まず、4000字前後にも及ぶ文章を読み切る集中力と読解力を鍛えるのに最適でしょう。中学入試の説明文読解では平均して4000字程度(文庫本約10ページ分)の分量が出題される傾向にあり 、本書を読み通すことで長文に慣れるトレーニングになります。加えて、論説文特有の構造(問題提起→議論→結論)や筆者の主張の組み立て方が明確なので、子どもと一緒に「主張と根拠」を整理する練習にもなるでしょう。「なぜ筆者はこう考えるのか?」「この例(エピソード)は何を説明するためのものか?」といったポイントに注意しながら読むことで、論旨把握の力が養われます。
もっとも注意したいのは、「ただ本を子どもに与えるだけではいけない」という点です。物語文と違い、こうした論説調の文章は子ども一人で読み進めるのは難しく、入試問題として一部が切り取られているからこそ理解できる場合も多いのです。保護者の方が先に目を通し、重要箇所に線を引いたり要約を一緒に考えたりするなど、伴走しながら読ませる工夫をお勧めします。仮に通読が難しいようであれば、無理に最初から最後まで読ませる必要はありません 。興味を引きそうな章から読んでみたり、親御さんが内容をかみ砕いて聞かせてあげたりするだけでも十分効果があります 。
最後に、本書を親子で読む意義は受験対策に留まりません。不確実な世界に向き合うための心構えを説く内容は、受験期のメンタルケアやこれからの生き方の指針としても大いに参考になります。読み終えた後にはぜひお子さんと感想を語り合ってみてください。「失敗を恐れず挑戦することの大切さ」や「自分で選んだ道を大切にする生き方」など、感じたことを共有することで、お子さんにとって受験勉強の枠を超えた学びとなるでしょう。中学受験という大きな挑戦に向き合うご家庭だからこそ、この『わからない世界と向き合うために』が教えてくれる前向きなメッセージを活かし、親子二人三脚で次のステップへ踏み出していただきたいと思います。