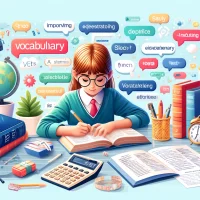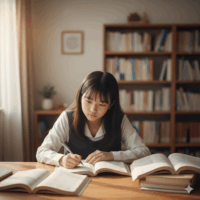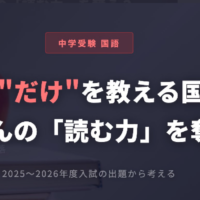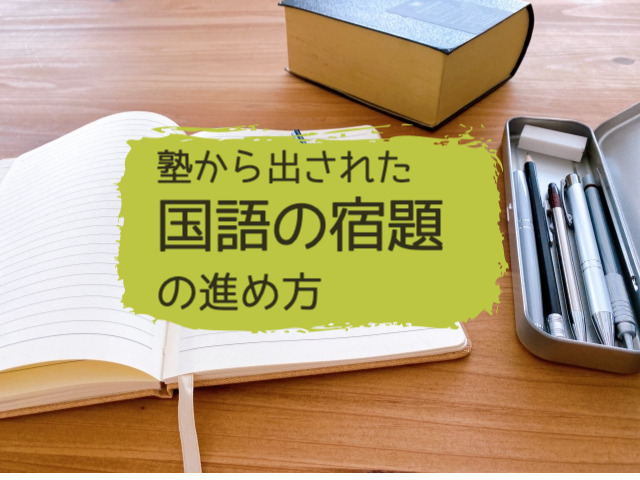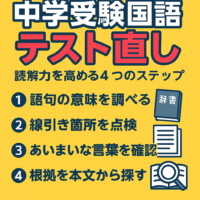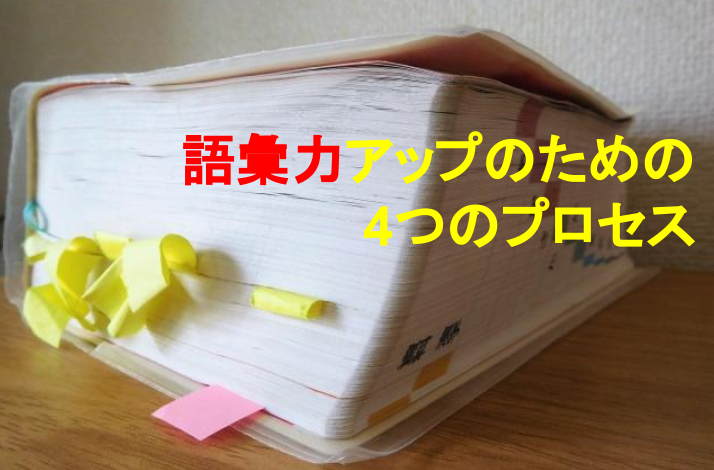【中学受験】物語文読解における「心の成長」のつかみ方|主人公の苦悩を理解し、成長のプロセス把握する
中学受験において、物語文の読解スキルは非常に重要な要素の一つです。
物語に登場する登場人物たちの心情や思考を理解し、ストーリーの展開を把握することが求められます。
しかし、これまで物語にあまり触れてこなかった子も多いでしょう。物語を通して読む機会が少なかった子などは中学受験向けの物語読解に苦手意識を持っている生徒も多く、その対策に悩む保護者もいることでしょう。
中学受験の物語読解において出題される文章の多くは青少年・少女が主人公であり、彼らの「心の成長」がテーマになるものが大変多く見受けられます。
従って以下のような心情変化のパターンを把握しておくと展開の予測が出来て読みやすくなります。ある程度の予定調和がわかっている方が人生経験が圧倒的に不足する子どもたちにとっては理解がしやすくなるのです。
1 始めは辛いことに遭遇し内向きな気持ちになりがち
物語の冒頭には、主人公が何かしらの困難に直面している場面が描かれることが多いです。この時点では、主人公は辛い出来事に直面しており、内向きな気持ちになりがちです。ここでは、主人公が何に苦しんでいるのかをしっかりと理解することが大切です。
例えば、「大切な試合の前に大怪我をしてしまって試合に出られなくなる」などがその典型例です。
小中高生が主人公である場合、こういった大きな試練に耐えきれず負の感情があふれ出してしまうことが多くあります。
結果周囲との人間関係も悪化するなど様々な事柄が悪い方に話が進んでいきます。
2 あることがきっかけで他者の思いに気づく
物語の中盤には、主人公に何らかの変化が訪れます。例えば、主人公が他の登場人物と接したことで、自分自身や周りの人々について新たな気づきを得たり、成長したりすることがあります。
この時点では、主人公が何に気づいたのかを理解することが大切です。例えば、「自分が受験に向き合うだけでなく、友達や家族の思いにも気を配ることが大切だと気づいた」という場合、主人公が自分勝手な考え方から脱却し、他者の視点に目を向けるようになったことが想像されます。
ここで心情がマイナスの状態からプラスに変化する兆しが見え始めます。
そのときに多用されるのが「情景」です。
明るい兆し、何かが変化する兆しが風景や天候に表されることがあるのでそういった点にも十分注意を払って読みましょう。
3 最後は他者と寄り添って前向きに歩き始める
物語の結末では、主人公が自分自身や周りの人々と対峙した結果、成長した姿勢で前向きに歩み始めるこ
ます。この時点では、主人公がどのように成長したのかを理解することが大切です。
例えば、「今まで自分を支えていてくれたチームメイトや両親の思いに気づき心を開く」という場合、主人公が自分自身や周りの人々に対してより理解を深め、新たなステージに向けて前進するようになったことが想像されます。
このように、物語の展開には定型パターンがあります。これらのパターンを意識的に把握することで、物語の理解が深まり、物語読解のスキルアップにつながるでしょう。また、物語に登場する人物たちの心情や思考に共感することも重要です。そのためには、豊かな想像力や感性を磨くことが大切です。親子で本を読みながら、物語の世界に浸り、豊かな心を育てていくことが、物語読解力の向上につながるでしょう。
何に気をつけて読むべきか?
最も重要なのは心情の変化です。
日頃から心情表現に線を引く練習をしておきましょう。またできる限りその心情を「プラス」と「マイナス」で分類しておくとさらに理想的です。
今回扱った「心の成長」をテーマにした物語文の場合、「他者の思いに気づく」あたりで「マイナス」と「プラス」の心情が入り乱れることがよくあります。
「マイナス」が続いていた心情に「プラス」の兆しが見え始める。この瞬間を情景や比喩で表されることが多く、問題にもよく扱われます。
上記のパターンを把握していれば自ずからこの「変化の兆し」を見逃さないように注意を払うことができるでしょう。
よくある主人公の試練ベスト10
- 学校でのトラブルや不祥事
- 友人関係のトラブルや裏切り
- 経済的な問題や困難
- 家族関係の問題や不和
- 病気や怪我による身体的な困難
- 自分自身の限界や課題に直面する
- 大切な発表会など人前での失敗
- 芸術的な才能を見失う
- 信頼していた人物の裏切りや欺瞞
- 失恋や片思いの失敗
主人公がこういった何らかの困難に直面して、その状況を克服するために苦闘する姿が描かれることが多いです。登場人物たちの挫折や苦悩が描かれることで、読者は共感や感情移入をすることができ、物語に深みが生まれるという面もあります。
お子さんがこうした試練を経験したことがないと言うケースも多々あると思います。
日頃から読書やドキュメンタリー番組などを通じて様々な人生における困難を疑似体験しておくことも大切です。