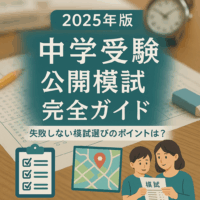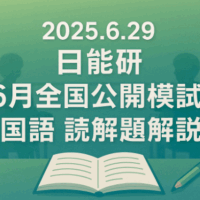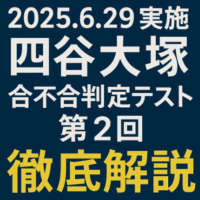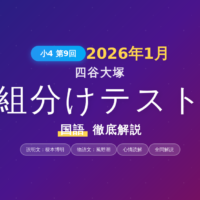- ホーム
- 模試・塾テキスト解説
- サピックス 6月マンスリー確認テスト 大問3 説明文解説
サピックス 6月マンスリー確認テスト 大問3 説明文解説
今回のマンスリー大問3は小川仁志氏の著作「中高生のための哲学入門―「大人」になる君へ」より、合理主義と引きこもりに関する文章が扱われました。九○年代から現代に至るまでの引きこもりの問題と、その背景にある合理主義の問題点について述べられた内容です。
九○年代は合理主義が行き詰まりを見せ始めた時期であり、その結果として様々な社会問題が表面化しました。引きこもりもその一つであり、合理主義の競争と画一性が引きこもりの原因とされています。筆者は自身の経験を通じて、過度な合理主義の追求が問題の本質であると指摘し、多様性を認める社会の重要性を強調しています。
重要語句・表現
- 合理主義(ごうりしゅぎ): 効率や理性を重視する考え方。
- 引きこもり: 家に閉じこもり、外部との交流を避ける状態。
- 功利主義(こうりしゅぎ): 「最大多数の最大幸福」を追求する思想。
- 八〇五〇問題: 80代の親が50代の引きこもりの子供を養う問題。高齢化社会における大きな課題となっている。
重要問題解説
問2(2)筆者は引きこもりについてどのように考えていますか
正解
ウ 社会の側に問題があったのだから、社会に適応できないことで引きこもりになる人が増えるのは当然の結果である。
筆者は、過度な合理主義や競争が引きこもりを引き起こす原因であると述べています。社会の仕組みが個人に過度なプレッシャーを与え、結果として引きこもりが増えるのは、社会の仕組みに問題があるからだとしています。これにより、引きこもりになる人が増えるのは当然の結果であると考えています。
他の選択肢の誤りの根拠
ア 社会の仕組みから脱落する人がいるのは仕方がないが、引きこもりは人数が多いので社会の仕組みの方に問題がある。
- 一部正しい要素を含んでいますが、筆者は引きこもりが「仕方がない」とは考えていません。むしろ、社会の仕組みの方に問題があると強調しています。
イ 引きこもりを社会に適応できない負け組のように扱うのは間違いであり、人間らしい人として高く評価すべきである。
- 筆者は引きこもりを高く評価すべきとまでは言っていません。引きこもりが人間らしい正常な反応であると主張していますが、それを高く評価するとは言っていないため、適切ではありません。
エ 引きこもりは大きな社会問題であるため、悪いのは本人だけではなく周りの人にも責任があると認識する必要がある。
- 筆者は引きこもりを社会問題として認識していますが、周りの人の責任については言及していません。主に社会の仕組みや合理主義の問題点を指摘しています。
問4「永遠の敗者としてレッテルを貼られてしまいます」とあるがどういうことですか。
「どういうことですか」という形で問われているので「同内容の言いかえ」を求められていると考えます。言いかえの場合、抽象的な言葉、具体的すぎる言葉、何を指すのわからない指示語、比ゆ、慣用的表現、ことわざなど、少しわかりづらい表現に注目しそれらを【誰にでもわかるレベル】に言いかえるように意識してみましょう。今回は以下の2つの言葉に注目しましょう。
「永遠の敗者」・・・長い期間、社会から低く評価されること
「レッテルを貼られる」・・・一方的で偏った見方をされ、(主に低い)評価を押しつけられるされること
これらを本文内容にあわせてまとめるとよいでしょう。
問6「学校というところは,そんな普通に溢れています」とありますが、ここでは筆者はどのようなことを言いたいのですか。
正解
エ 感じ方の違いを無視して、学校の様々な場面で多数派の考えに従うように求められることが、子どもを不登校に追い込む一因になっているということ。
筆者は、「普通」という概念が押し付けられることで、個々の子どもの感じ方や考え方が無視され、多数派に従わなければならない状況が生まれていると述べています。このような状況が、子どもたちにとって大きな負担となり、不登校や引きこもりの原因の一つになっているとしています。
他の選択肢が間違っている理由
ア 多くの人に合わせることをルール化することによって、価値観の違いに苦しむ子どもが増えているので、学校にあるルールはすべて撤廃すべきだということ。
- 筆者は学校のルールをすべて撤廃すべきだとは言っていません。むしろ、多様性を認めるために競争から降りる自由や復活する道を用意するべきだと述べています。「すべての」特に言い過ぎてルールの【完全撤廃】を主張しているわけではないため、適切ではありません。
イ みんなが普通だと考えていることにあわせて行動しようとしない、協調性に欠けている子どもは、学校だと特別扱いされてしまい苦しんでいるということ。
- 筆者は協調性に欠けている子どもを特別扱いすることについて述べているわけではありません。普通を押し付けることで子どもたちが苦しむ状況を批判しているのであり、協調性の問題に焦点を当てているわけではありません。
ウ 普通という言葉には、良し悪しの価値観は含まれていないのに、有益であるという意味を込めて使っている学校の現状に目を向ける必要があるということ。
- この選択肢は前半だけは正しく見えますが、筆者の主張の核心は「普通」という概念が押し付けられることで個々の違いが無視され、その結果として子どもたちが不登校や引きこもりになるという点です。価値観の問題も含まれていますが、主要な論点は普通を押し付けることによる個々の違いの無視にあります。
問7「みんなが特別になればいい」とありますが、筆者は学校をどのように変えればよいと考えていますか
問4と同様にわかりやすく言いかえる問題と考えて良いでしょう。「みんなが特別」という部分が比ゆ的でわかりづらく、本文の内容から筆者の考えをくみ取り言いかえる必要があります。
まず結論から考えます。
筆者は学校をどうしたいのか、一言で考えることが重要です。
最終段落で「【大事なことは】、一人ひとりのペースを重んじることだと【思います】。」と述べています。【大事】【思う】と言った表現から「筆者の主張」が述べられていることがうかがえます。
そして近年の説明的文章のキラーワード「多様性」を組み込めればほぼ完璧な結論が作れます。
解答欄の大きさから判断して、この結論だけでは要素が不足していると考えられます。
ここでは【対比】的な内容を上にのせて「〜ではなく」と打ち消しでつなげるとと良い形になりそうです。文字数を増やしたいとき【対比】を上乗せするテクニックは重要です。
「普通であること美徳とされる」をそのまま使っても良いですし、「普通であることを強制する」「普通でないと評価されない」などわかりやすくアレンジしても良いでしょう。