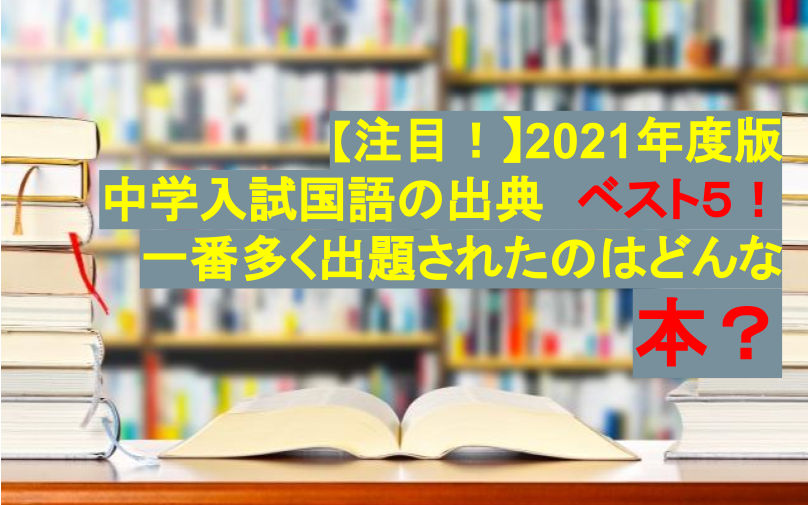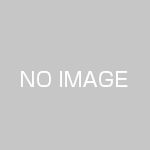中学受験にオススメの辞書 -中学受験に小学生向けの辞書はNG!?ー
中学受験の勉強をサポートするために、適切な辞書を選ぶことは非常に重要ですお子さんの学習段階や目的・好みに合わせて、最適なものを選びましょう。
紙の辞書 vs 電子辞書のメリット・デメリット
紙の辞書と電子辞書にはそれぞれ以下のようなメリットとデメリットがあります。紙の辞書のメリット:
- 一覧性が高く、意味・用法・用例を一度に確認できる
- 直接書き込みができ、マーカーを引いたり補足情報を書き込める
- 電子辞書と比較すると安価なものが多い
- 持ち運びがしづらく、重くかさばる
- 調べるのに時間がかかる
- 持ち運びがしやすく、コンパクト
- 前方検索・後方検索・あいまい検索など様々な検索方法ですばやく調べられる
- 履歴機能や暗記カード、音声再生など学習に便利な機能が充実
- 紙の辞書に比べると値段が高く、扱いに注意が必要
- 一度に見られる情報量が限られ、一覧性は紙の辞書より劣る
個人的には基本となる語彙や常識が不足する小学生は少し手間がかかっても一覧性が高く、目的の言葉以外からも多くの情報を得ることが出来る紙の辞書をオススメします。
中学受験に役立つ国語辞典の特徴
気をつけなくてはいけないのは、中学受験対策として辞書を活用する場合、最終的には【小学生向けの辞書】では調べたい語彙をカバーできなくなるということです。小学生向け辞書はあくまで教科書や児童書に使われるであろう言葉を中心に掲載しているのに対して、中学受験で扱われる文章は一般の大人が読む新書や小説などが大きな比率を占めますから、小学生向けの辞書が中学受験で扱われる語彙をカバーしきれなくて当然です。
例えば「人口に膾炙する」「アジャイル」「アサーティブ」「ためつすがめつ」「おためごかし」・・・これらは近年の中学受験の入試問題で扱われた言葉です。これらは小学生向け辞書には掲載されていないことが多いです。
また小学生向けの辞書は語彙の解説が平易になっていることや、対義語、類義語、例文などの解説もかなり簡素であり中学受験の知識としては著しく不足します。
多くの塾において小5向けの教材あたりから小学生向けの辞書に掲載されていない語句が扱われ始めてきます。こういった難しい単語の意味を理解するに、収録語数が多く、詳しい語釈が書かれていることが必要です。また集中して勉強するためには、調べたい言葉がすぐに引ける使いやすさも重要です。50音順の配列や、大きめの文字、分かりやすいレイアウトなど、自分が使いやすいと感じる辞書を選びましょう。中学受験対策が本格化する小4以降、早めに【中学生向け】の辞書に切り替えると良いでしょう。 国語辞典を活用して語彙力を高めることが、中学受験の国語の成績アップにつながります。
三省堂「例解新国語辞典」の特長
三省堂の『例解新国語辞典』は、中学生向けの辞書として高い評価を受けています。第十版は2021年2月10日に発行され、最新の教科書に対応するために全面改訂されました。この辞典は、6万語以上の語句を収録し、用例や類義語・対義語、敬語の使い方など、周辺知識の掲載が非常に豊富なのが特徴です。これは受験対策として非常に有効でしょう。また、UDデジタル教科書体を採用し、読みやすさにも配慮されています。さらに、誤用しやすい言葉や方言についての注意情報も充実しており、学習者の理解を深めるための工夫が随所に見られます。
旺文社「標準国語辞典」
旺文社標準国語辞典は、中学生から高校生までの学習者に適した国語辞典です。第八版は2022年2月に発行され、約76,000語を収録しています。語釈や用例が豊富で、古語や慣用句なども充実しているため、国語の受験勉強に役立ちます。また、カタカナ語や外来語の語源解説、ことわざや故事成語の説明なども詳しく掲載されており、単に意味を調べるだけでなく関連する言葉の知識を深めるのに最適な辞書と言えます。さらに、同音異義語や使い分けが難しい言葉についての解説も充実しているため、正しい言葉の使い方を学ぶことができます。特装版には、「言葉の使い方ガイド」や「文法・敬語ガイド」などの付録が付いており、生きた言葉の知識を身につけるには最適です。紙面のデザインもカラフルで見やすく、長時間の学習でも疲れにくいよう工夫されています。中学受験から大学受験まで長く使える、頼りになる国語辞典です。
大修館書店「明鏡国語辞典」
『明鏡国語辞典』は、大修館書店から発行されている国語辞典で、2002年の初版発行以来、その斬新な編集方針で注目を集めています。 新語や俗語を積極的に採録し、「バズる」「リスケ」など他の辞書には載らない言葉も収録しているのが特徴です。 また、「喧々諤々」を「喧々囂囂」の誤用とするなど、言葉の誤用を丁寧に指摘・解説している点も『明鏡国語辞典』ならではの特色と言えます。編者の北原保雄氏は、澄み切った鏡に日本語の現在を正しく映し出したいという思いから「明鏡」という名を選んだと述べています。 2021年1月に発売された第三版では、「SDGs」「サブスク」など新語を追加し、約7万3000語を収録。「品格」欄を新設し、改まった場面でも使える類語を掲載するなど、時代に合わせて内容を一新しています。
まとめ
このように様々な特徴を持つ各出版社の辞書ですが、まずはお子さん自身が書店で辞書を手に取ってデザインや体裁が良いと感じるもの、内容が面白いと思えそうなものを選んでみることが大切です。選りすぐりの「マイ辞書」を持つことで少し面倒に思える言葉の意味調べの動機づけにもつながるでしょう。また、継続して辞書を使い続けるには、調べた言葉にマーカーを引くなどして調べた履歴が一見して分かるような工夫をすると、保護者の方と調べた言葉を共有しやすくなり成果がわかりやすくなり動機づけにつながります。一度引いたことのある言葉について保護者から質問するのも良いですね。マーカーをたくさん引くことに達成感を感じ、辞書引きの動機づけになっているお子さんも多くいらっしゃいます。また辞書を学習の合間に読み物として「ランダムに開いたページを読む」というのも語彙の幅を広げるには非常に有効か学習方法です。
長い中学受験の相棒となるような辞書が見つかることを願っています。