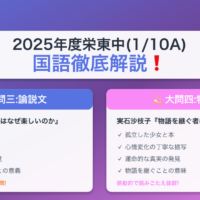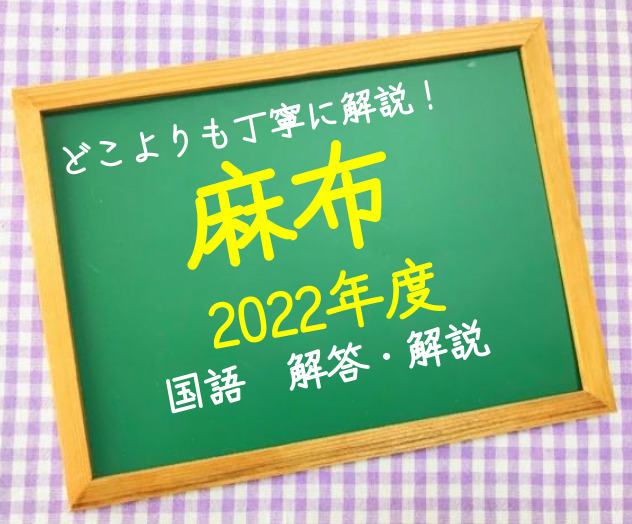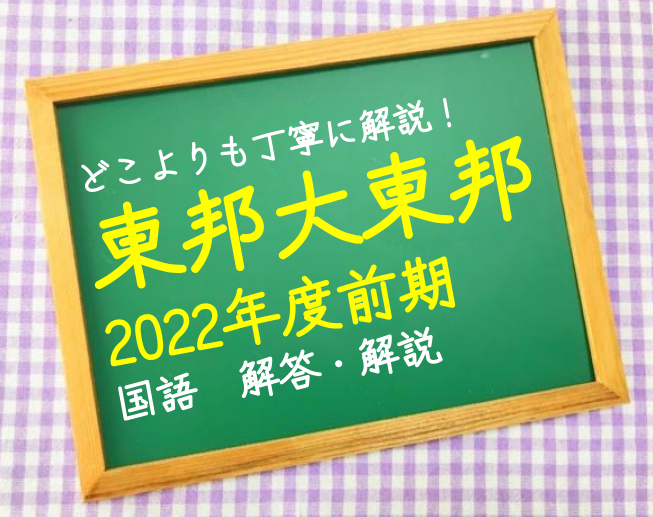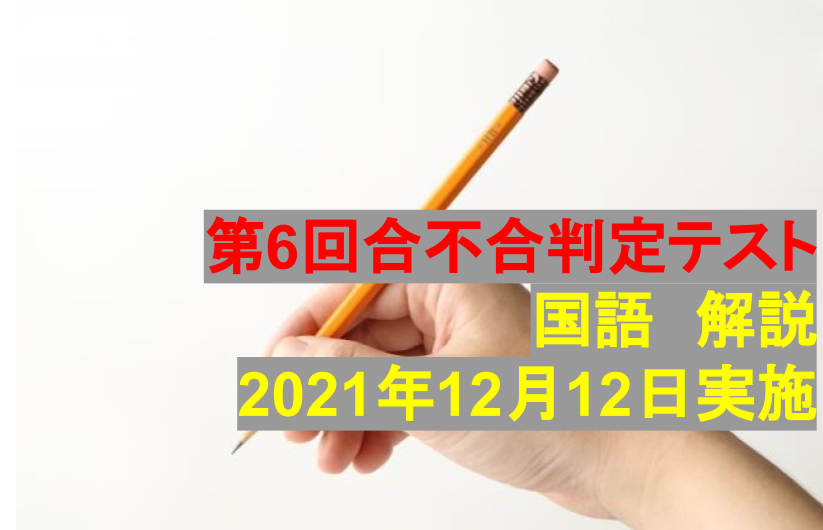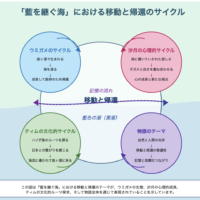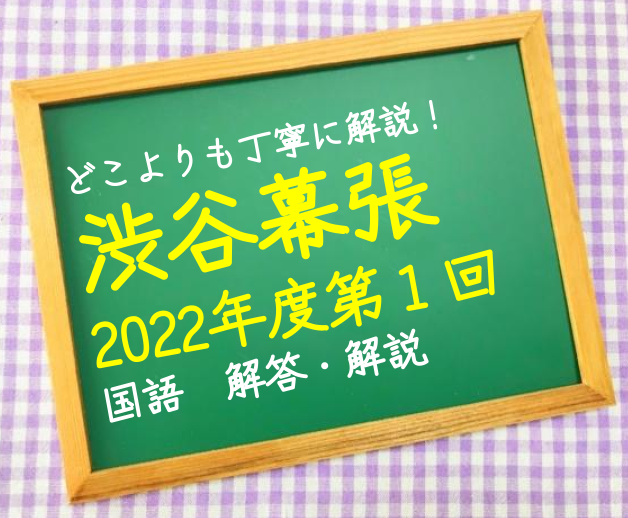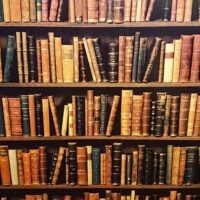【徹底的に丁寧な解説!】2021年度栄東中学A (1/10) 国語 過去問 読解問題
首都圏で最も受験生を集める埼玉の代表的進学校です。
都内最難関・難関校を目指す受験生たちも栄東を皮切りに入試がスタートするケースが非常に多く、その後の入試を占う極めて重要な入試になります。
過去問を丁寧に取り組み、万全の準備で挑みたいところ。
今回は読解問題に焦点を当てて解説してまいります。一問一問解答根拠を含めて丁寧にご説明しています。市販の過去問解説書で理解ができなかった部分の確認、直前期の振り返り、解き直しに活用してください。
※なお、栄東中は事前の説明会で入試問題の出題傾向についてかなり詳細にわたって説明をしてくれます。説明会に参加されていない場合はお通いの塾などに相談してみるとよいかもしれません。

大問三 説明文「最後の講義-どうして生命にそんなに価値があるのか」福岡伸一
全体所感
自然科学分野の文章らしく使われる用語に一部難解なもの(アイソトープ、同位体、平衡、相補性、自己同一性など)が使われています。それらの言葉について一つ一つの解説が丁寧にされているわけではありませんが、自然に理解ができるような流れて文章が構成されており、全体の内容は理解しやすい部類に入ります。
一方で、同じ生物の個体であっても細胞・物質レベルでは入れ替わっているという状態にイメージが及ばない子にとっては全く理解ができないと感じさせてしまうリスクもあります。
今回このような状況であったお子さんについては以下のサイトなどで基本的な知識を身につけてから再度トライするとよいでしょう。
https://health.suntory.co.jp/professor/vol32/
問一
「生命は毎日、食べ物を食べ続けなければいけない存在です。私も一日3度、ご飯を食べています。どうしてでしょうか?」とありますが、この問いに対する答えが最もわかりやすく説明されている段落を探し、初めの五字を抜き出して答えなさい。
文章「冒頭の問いかけ」ですから『話題』を示すことは明白。そしてその答えが書かれている箇所を「段落」単位で探し出せという指示です。
筆者はこの「なぜご飯を食べるのか」という本文全体の話題に関わる問いについてはすぐに答えを出しません。
食べた食料の行方を調べる実験を行うことで「なぜご飯を食べるのか」ということが少しずつ判明していくプロセスを読みながら理解していれば、本問の解答はシェーンハイマーの実験の後に隠されていることに気付けるかと思います。
このように文章全体の構造を俯瞰してとらえ、解答に関連する表現が書かれたおおよその場所を予測しておくことは重要です。
問二
「機械論的な考え方」とありますが、この内容として最も適切なものを選び、答えなさい。
傍線部の「言換え」た内容の選択肢を選ばせる問題。
※「言換え」=同内容を言葉を変えて表現すること
今回は「機械論」という言葉がどんな内容を指すのか考えます。
本文傍線部の直後「食べ物と生物の関係も、例えば、自動車とガソリンの関係に置き換えて説明されていました。」から「機械論」とはこの考え方を指すものと予測されます。「生物を機械に置き換えて考える」といった内容であろうことが予想できればベスト。
ア:機会が人間より正確⇒書かれていないので×
イ:生物は機会を操る⇒書かれていないので×
ウ:生物の構造や仕組みを機械として捉える=つまりは「生物が機械と置き換えられる」ことになるので○
エ:生物に役立つ機械⇒書かれていないので×
オ:機械と生物の違いを研究⇒「置き換え」は「違いの研究(≒比較)」とはずれるため×
問三
「インプットとアウトプットの収支がぴたりと合うかどうか」とありますが、これは具体的に何を述べているのですか。
「これは具体的に何を述べているのですか」とありますので、問一同様に本文内容の「言換え」問題です。正しく言換えるためには言葉の意味を正しく解釈する必要があります。
「インプット」・「アウトプット」の概念が理解できているか。「収支」の意味を知っているかがすべてと言っても過言ではないですね。
・インプット:外部に合ったものを内部に取り入れること。入力。
・アウトプット:内部にあるものを外に出すこと。出力。
・収支:収入と支出(入ってくるものと出ていくもの)
このように理解できれば「入ってくるものと出ていくもののバランスが取れている」という内容の選択肢を選ぶのは難しくないはず。
選択肢【ウ】「体内に入った食べ物の粒子(インプット)が体から出ていく食べ物の粒子(アウトプット)と同じ量か(収支)を調べている。」が正解になります。
問四
「シューンハイマーは食べ物の粒子に印をつけ、生物の体の中のどこに行ったかを追跡するという実験を行いました」とありますが、この実験はどのような結果になりましたか。
傍線部4で「実験行いました」と述べたのち、実験の内容を説明し、さらに傍線4の9行あとに「結果は意外なものでした」という記述があります。
ここから設問で求められている「結果」について詳しく説明されています。この実験結果に関する記述は次の中略のまえ「この実験から~」の表現で始まる段落まで続きます。
この実験結果に関する段落をすべてよく読んで実験結果から何がわかったのかを簡単にまとめると
①食べ物は体の一部に成り代わってた
②体重にほとんど変化がない
以上2点になります。
①については「食べた食べ物の半分以上は燃やされることなく、マウスの体の尻尾の先から頭の部分、体の中、いろいろなところに溶け込んで、マウスの一部に成り代わっていたのです。」
この部分を解答として適切にまとめます。
記述の解答には「具体例」や「比喩」を入れてはいけないという原則があります。この問題の場合「マウス」「尻尾の先から頭」などの具体例を避けてまとめるとよいでしょう。
最後に②を付け加えれば答案の完成です。
問五
本文中の【Ⅰ】にはどのような内容が入りますか。空欄に当てはまるように自分で考えた例を二十字以上三十字以内で答えなさい。ただし「だけでなく」という言葉を必ず使うこと。
「自分で考えた例」とありますので、本文の内容だけでなくオリジナルの例を挙げる必要があります。また、読解の空欄補充問題での大原則、空欄を含む一文および前後の一文の表現を一字一句漏らすことなく読み込むことが重要です。
今回は空欄1⃣の前の表現に注目すると以下の表現が重要になりそうですね。
「これを自動車とガソリンの関係に置き換えると~」
上記の表現にについて以下2点を意識して探していきます。
①指示語「これ」が指す内容はどこにあるか。
②「自動車とガソリンの関係」の説明はどこにあるか。
①については直前の表現「食べたものの半分以上は燃やされることなく、~マウスの一部に成り代わっていた」の部分を指します。
②については傍線1のあとの「つまり」(←まとめ・言換えの重要ワードです!)の後に注目。
「自動車を動かすためにはエネルギーが必要なので、ガソリンを補給します」
の部分が使えそうです。
ここまで材料をそろえたうえで問題条件にある「だけでなく」をどう使うかをイメージしながら解答の構造を考えます。
すると
「食べ物は体を動かすエネルギーとして燃やされる」だけでなく「体の一部に成り代わる」
という内容が思い浮かぶと思います。これを自動車の例(上記の②)に当てはめ言換えます。
「ガソリンは自動車を動かすエネルギーとして燃やされる」だけでなく「車体の一部に成り代わる」
解答はこのような内容になりそうです。あとは字数調整のために不要な個所をカット。
「ガソリンは燃やされるだけでなく車体の一部に成り代わる。」でよいでしょう。
※学校解答では「車体」ではなく「タイヤ」とありますがここは「自分で考えた例」にあたる部分なので、自動車の一部分であれば何でもよいでしょう。
問六
「生物学的には違う人が言ったことですから」とありますが、これはどういうことですか。
「どういうことですか」と聞かれていますので言換え問題。赤字の部分を別の表現で言換えるとどうなるかを考えます。傍線を含む一文と前後の文は精読することが重要です。
すると傍線5の一行前「物質レベル(=生物学的)ではほとんどが入れ替わっている(=違う人)と言っても過言ではないほど変わってしまっている」とあり、問題と関係が深そうです。
このように、いきなり選択肢の吟味に入るのではなく傍線の前後で内容に深くかかわりそうな部分をよく読み直してから選択肢の吟味に入るように心がけましょう。
一つひとつの選択肢の文が非常に長いので部分部分でスラッシュ(/)を入れて区切りながら吟味をしましょう。
ア:細かい粒子と約束していることになる・・・×
イ:人は一人一人輩出の仕方が異なっている・・・×
ウ:前の自分は~今の自分に比べて劣っている・・・×
エ:○
オ:約束した当時から約束をはたすときまでの期間に何人もの私・・・×
問七
こちらも空欄補充ですので空欄を含む一文と前後の文を丁寧に読みましょう。
Ⅱについて
「絶え間ない流れの中で合成と分解を繰り返しているさま」と「矛盾したように聞こえる」
この2点に注目。
「変わる」「変わらない」が矛盾したかのように表現されているもの。つまりは「変わるけど変わらない。」「変わらないけど変わる」といった内容のア・ウ・オが候補に挙がります。
Ⅲについて
空欄前後「矛盾したように聞こえますが」(=逆接)、「~のが私たちの体なのです」とありますので、一見矛盾に見える【空欄Ⅱ】の内容を受けて【空欄Ⅲ】でその矛盾を解消する形になろうことを予測します。
以下のように判断します
ア:大きく変わってしまわないために小さく変わる・・・Iの矛盾の解消
イ:小さく変わり、大きくも変わる・・・「変わらない」の要素がなく×
ウ:変わりたい部分と変わりたくない部分・・・本文に記載なく×
エ:変化を調節・・・「変わらない」の要素がなく×
オ:小さく変わることすらしない・・・本文に記載なく×
問八
この文章を読んだ生徒の会話を読んで本文内容と「一致しない発言」をしている生徒を選ぶ問題。
会話とはいえ比較的長めの文が続きますので読み落としに注意して読み込む必要があります。
特に難解な言葉が使われている場合に落ち着いて本文内容と照合して確認をする冷静さが必要です。言葉の意味が正確にわからなくても本文内容と合致しているかどうかは判断可能です。
言葉を知らない、わからないからといって大雑把になったりあきらめたりすることが無いようにしましょう。
今回は生徒Aの発言「自己同一性や記憶も相補性によって交換されていたよね。」の部分が間違い。
今回の文章のテーマである動的平衡の意味合い、つまり小さな変化を続けながらもその特性を失わないように大きく変わらないで自己を維持する生物の特性についてよく理解されていれば、「自己同一性」や「記憶」まで交換されてしまうことはありえないと分かるはずです。
大問四 物語文「永遠の夏をあとに」雪乃紗衣
全体所感
いじめを受けていた小学生の友情ストーリー。題材としては理解しやすいものの、回想シーンが多く、時間軸を中心とした場面の変動が激しくなっています。正しく全体をつかむためには注意深く読む必要があります。
今回の題材は、中学入試の定番である「家族」の存在感は薄く、大人はストーリーに登場するものの、視点はあくまで子ども同士の世界観の中でその関係性にフォーカスした内容になっていることにも注目したいですね。
また、情景描写が豊かでプラスとマイナスのコントラストがはっきりしているので、人物の発言や動作だけでなく、人物の心持を通して彼らの目に映った景色にも注目して読みたいところです。
問一
空欄を含む一文と前後の文を丁寧に読めば問題なく正答できるレベル。「あべこべ」「ぶしつけ」は意味があいまいであればしっかり辞書で調べておきましょう。
・校門には【A】身なりの記者が数人・・・記者の服装をあらわすのにふさわしい表現なので「イ」か「ウ」。
・(入学式に来ないと思われていた拓斗を見る周りの目を花蓮おばさんは周りを気にしないふりをする一方で)羽矢拓人はそんな様子もなく【B】視線やざわつきも全部体をすり抜けていくようだった。・・・奇異の目で見られているのを無視している様子から「エ」が本命。「イ」は違和感があるがなくもないか?
・他の小学生にはない【C】部分を、拓人だけは持っている。幼稚園児から抜けきれぬ新入生の中で、拓人だけが違っていた。・・・幼稚園児らしい状態と正反対の様子を選ぶと「イ」。他の「イ」候補(A/B)がここで消せる。
・相手の母親らは「羽矢拓人が自分の自分の子供らに怪我をさせた」と【D】言いがかりをつけた。・・・「が」に点がふってあることからわかるように拓人は被害者であるにもかからわず、加害者であるように言われたことを表す表現で「ア」
問二
「ここ」とはどこですか。本文中より一語で抜き出して答えなさい。
主人公の彰が現在いる場所を問われています。回想シーンが織り込まれていますので情景描写と時間軸に注意をしながら読み進めることが必要です。
風が吹くと一斉にさんざめく青い竹の葉音。木から降り落ちてくる光の粒を拓人と仰ぎ見た。
↑こちらは去年拓人と神楽を手伝った際の回想。拓人との思い出が「輝いて」見えているようです。
ここは何もない。冷え切り、のっぺりと全部が死んだ空間。
↑こちらが今、自分が置かれている環境。前述の拓人との思い出が今、彰が置かれている状況の「味気なさ」を対照的に浮き彫りにさせいます。
物語の舞台となる拓人と過ごした神社とは対照的で味気ない場所、、、つまりは塾ということになります。
「死んだ空間」の2行あとに書かれている「彰は席を立ち、自習室から出て行った。」との表現から答えが導き出せます。
問三
「小学校に入学する前から、彰は会ったことのない『羽矢拓人』を知っていた」とありますが「羽矢拓人」にまつわる話として本文の内容と一致しない許を次から一つ選び、記号で答えなさい。
彰は会ったこともない拓斗を知っていました。それは大人たちの会話から漏れ伝わったためです。
ということは大人たちの拓人に関する噂話が列挙されている箇所を丁寧に読めばよいということになりますね。
本文「幼稚園での親同士のひそひそ話~」からその9行あと「~可哀想だわねー」までを丁寧に読みましょう。
選択肢はやや長いので一かたまりごとにスラッシュ(/)をいれて部分ごとに吟味していきましょう。
なかなか見つけづらいかもしれませんが、選択肢「ウ」の「母親は仕事で出かけていることが多く」の
表現が×。
根拠は本文「若い母親はしょっちゅう出歩いていて家にいない。こないだその母親が年上の男と市中のレストランにいたのを誰々さんが見たようだ」。
これにより「仕事で出かけて」が合わなくなります。
問四
「実際そうなった」とありますが、どのようになったのですか。そのことがわかる「拓人」の様子を表した一文をこれより前の本文から探し最初の五字をぬき出しなさい。
「そうなった」の「そう」が指示語であることを意識しましょう。ただし、指し示す内容が指示語の前に書いてあることが多いですが今回は直後「入学式の翌日から男子連中は拓人をいじめの標的にした」を指します。
しかし問題の条件に「これより前」とありますので「いじめにあった様子」が書かれている部分を探します。ポイントは「拓人」の様子からいじめられていることがわかる個所です。
このような条件から問題が求めているのは「拓人が怪我をしている様子を表した」部分であろうことが予測できます。
読者がいじめの事実を初めて把握できる個所よりだいぶ前の離れたところにさらっと書かれている表現。「腕や足に切り傷や青あざをこさえた小二の拓人」とある部分がみつかるかどうか。
難易度が高くただあててもなく本文を探しても答えは見つかりません。
・いじめにあっていることがわかる部分
・拓人の様子が描かれている部分
・傍線部より前(傍線部より前にいじめの表記はないため状況で判断することになるだろうと予測)
上記のとおり条件を整理して順を追って探していきましょう。
問五
「理不尽をはね返さなかったら、理不尽がルールになる」とありますが、ここでは具体的にどのようなことを指していますか。
「どのようなことを指していますか」という言換え問題。言換えの記述は「もとの表現」を部分ごとに分解し、よりわかりやすい言葉に言換える、という作業が必要です。
今回の場合は「具体的に」という指示がありますので「具体的」かつ「わかりやすい」表現に言換えることとしましょう。
パーツ①「理不尽をはね返さなかったら」
本文「拓人は自分から喧嘩は売らないが、売られた喧嘩は買う。『拓人もやり返さないの』なんて養護教諭の馬鹿な言葉を~」の部分が具体的で使えそうです。
「売られた喧嘩を買う」または「いじめに対してやり返す」といった表現が具体的でわかりやすいでしょう。
パーツ②「理不尽がルールになる」
これに関する明確で具体的な表現は見つかりませんので自身の言葉で。
「理不尽」=いじめであることが明白なので「ルールになる」をどのように言換えるか。
ここはすぐに出てこなくてもお子さんに粘り強く考えさせてください。
「ルール」とはそれが正しいという判断基準。決まりごと。
いじめが正しい、それが決まりごとになるということですから、
「当然のこととなる」「あたりまえになる」「悪いことと思われない」などがふさわしいでしょう。
学校解答以外に
「売られた喧嘩を買わないといじめが当然のことになるということ。」(30字)などでもよいでしょう。
問六
「彰は拓人の後を追って石段をあがった」とありますが、それはなぜですか。
まず傍線を含む一文とその前後の文を読む。
重要なのは(羽矢拓人、お前、どうやってんの?)という彰の心理の部分。
彰は拓人に何かと問いかけています。それはさらにその1~2行前の部分。
「これ(=いじめ)が卒業まであと五年続くと思うと、目の前が真っ暗になる。」
とあります。拓人は入学式の時から奇異の目で見られながら全く気にせず「自然体」でおり、「別の大事な気がかりに気を奪われているかに見え」ており、いじめなど全く気に留めていないように見えます。
そんな拓人がどうしてそんな風に自然でいられるのか、いじめに苦しむ彰の心の声としてでてきたのが「お前、どうやってんの?」という言葉。
いじめにどう向き合っていけばよいのかを聞こうとしているのです。
傍線部の後ろ、「石段から足を滑らせて落ちても、今なら痛くないだろう」や「別の世界に行けそうな気がした」は石段を上る拓人を追いかける動機とは直接関係ありませんのでまどわされないように注意が必要です。
心の底では拓人に救いを求めている、それに真正面から向き合う拓人の様子が描かれていることから「ウ」を選びます。
ア:拓人が学校をさぼってどんな風に過ごしているのか確かめたかった・・・拓人に救いを求めているいるため×
イ:別世界に連れて行ってもらえる・・・別世界は自分の足で踏みこんでいるため×
ウ:けんかの強い拓人、仕返しができる、・・・・やり返そうという意志は感じられないので×
エ:○
オ:拓人に見守られながら~消えたかった・・・絶望は感じながらも「どうやってんの?」と救いを求めているため「消えたい」とまでは思っておらず×
問七
「団子のようにくっつき、自分がひきつぶされてぐちゃぐちゃになる」とありますが、この内容を四字熟語で表現するとどのような言葉になりますか。
団子のようにくっつき・・・周囲の人々に合わせて
自分がひきつぶされてぐちゃぐちゃ・・・自分の考えを失う
このように比喩表現をわかりやすい言葉に置き換えて考えましょう。
問八
「全然笑わなかった」「愉快そうにした」とありますが、この時の拓人の心情変化を説明したものとして最も適切なものを次から選び記号で答えなさい。
傍線7を含む一文「拓人は妖怪泥人間みたいな彰を、全然笑わなかった。」に注目。
ひどいいじめにあってボロボロな彰の様子を作者があえて「妖怪泥人間のよう」と表現した背景を読み取りましょう。子どもがみたら思わず笑ってしまうような泥だらけでひどいありさまをみて全く笑わない拓人の想いを浮きだたせる意図を感じ取りましょう。
同じくいじめにあってきた拓人だからこそ彰の姿を笑わずに受け止めたと解釈しましょう。
傍線8を含む一文とその前の文
「『むり』声がかすれた。『おれの心の傷はそれくらいじゃよくならない』『なんだそれ』と、はじめて拓人は愉快そうにした。『いいから、体の傷はちゃんと洗えよ』」
一時「目の前が真っ暗」になった彰に対し真正面から笑わずに向き合う拓人に対して、すがるような姿勢を全く見せずあくまで対等な友人として「むり」「心の傷はよくならない」などと素直に思いをぶつけてくる姿に、拓人が親近感を持つ様子が「なんだそれ」といったセリフから読み取れます。
男の子動詞の親しい間だからこそ使われる気遣いのない、少し雑な言葉遣い(むり、なんだそれ、等)。こういった繊細な言葉遣いにも反応していきたいですね。
ア:○
イ:慎重な対応・・・真剣に受け止めたが慎重とは少しずれる。甘え・・救いを求めるような姿勢は見せていないので×。
ウ:不審に思って警戒・・・不信感は感じさせられる表現がなく×
エ:冗談を言う彰・・・「心の傷は~」「むり」という表現を指しているのだろうが、思いを素直にぶつけただけで冗談というレベルではないので×
オ:彰を疎ましく…疎ましく感じていた様子が全く描かれていないので×
問九
「隣に並んできた拓人を、彰はまじまじと見返した」とありますが、この時の彰の様子を説明したものとして最も適切なものを次から選び記号で答えなさい。
この文書のクライマックス。主題が描かれている部分ですので全体の物語の流れとその背景にある作者の意志を感じ取りながら答えたい問題です。
この文章では神隠しに合ったと言われ周囲から奇異の目で見られても、いじめられても気にとめず、周囲に合わせず我が道を行くミステリアスな拓人、と同じくいじめにあい家族の理解も得られず孤立し苦しむ彰が出会い、本当の友情が芽生えるストーリーです。
そのクライマックスシーンであることを強く意識する必要があります。
今回自由記述である問10を除けば、本文内容にかかわる問としてはこの問9が最後の問題です。
大問の中の最後の問題というのはその文章全体のテーマや主題を掘り下げた問題になることが多いということは理解しておきましょう。
傍線9の5行前の神社から帰るシーン「夕日が雲と稜線を金色に縁取り世界は薄暗かったが、綺麗だった。」から、外の世界は暗い(=いじめ終わったわけではないし、家族の理解も得られていない)が夕日を綺麗に感じる前向きさは取り戻せた(=真の仲間を見つけた)ととらえましょう。
その後「昨日の神社のことはもうかすんでいた。」という表現からまた現実の生活に引き戻されている様子も併せて読み取りたいところ。
拓人と分かち合えたように感じた真の友情は本当に現実なのかあいまいになっています。
そこに「叢越、心の傷はどーだ」と拓人に親しげに声をかけられたことに驚き、昨日の出来事は夢ではなかったと実感。「最高のオレ」を感じるに至ります。
ア:拓人が心の傷をえぐる・・・見当違いなので×
イ:やめてほしい・・・その後の「最高のオレ」からもわかるよに前向きな気持ちなので×
ウ:自分かどうか半信半疑・・・周囲から完全に浮いている拓人がほかの人に話しかけるとは考えづらく、しかも「叢越」と名前で呼んでいるため×
エ:夢だと思っていた・・・そのような思いはあるかもしれないがあまりに断定的で×
問十
省略。
22年度A・B入試では自由記述は出題されないとの情報があります(確定ではありません)。
まとめ
いかがだったでしょうか。
一部解答根拠を見つけづらいものもありますが、基本に忠実に読み落としの内容に読み進めることで高得点を狙える問題だと思います。なかなか高得点が取れないお子さんは、今回の解説をじっくり読み、数日時間をおいてから再度解き直すことをおススメします。
特に黄色のアンダーラインを引いてあるところは国語の読解問題全般で気を付けていただきたいポイントですので、ここだけ何度も繰り返しチェックするのも有効です。
ちなみに得点力アップのための解き直しのやり方はコチラ↓の記事もご覧ください。
千葉の市川中の過去問(2021)も解説しております。↓ご参照ください。